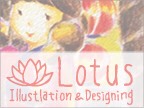◆ ライナーノーツ/演出後記 ◆
【ライナーノーツ】
『マイ・スウィート・スウィート・ホーム』の作者であり、友人・田中役を演じた東浦弘樹です。たくさんのお客さまにおいでいただき、心から感謝しております。
作者が作品について語るのは野暮かと思いますが、あの芝居のねらいは次の3点でした。
・ 恋は若者だけのものではない、中年や熟年の男女も若者と同じようにひとを愛するし、また愛されたいと願うものだということを示したい。
・ 「自分の人生はこれでよかったのか」、「別の人生もありえたのではないか」という不安、人生の節目に誰にでも訪れうる精神的危機を描きたい。
・ いい年をした男女が必死になってばかなことをしている或る意味みっともない姿に人間のみじめさと、その奥に潜む真実を示したい。
ポイントとしては次の4つを挙げることができます。
① 妻(洋子)は何に怒っているのか
② 夫はどのようにして妻を寝室から出てこさせるか
③ 友人、田中の役割
④ 結末のもつ意味
順を追って説明いたします。
① 妻(洋子)は何に怒っているのか
妻は決して夫に対して怒っているのではありません。彼女は言います――
「あなたと結婚したことを後悔してるわけじゃない。あなたのためにご飯をつくったり掃除をしたり洗濯をしたりするのも、決していやじゃなかった……
でもね、この歳になるとふと思うことがあるの、別の人生もあったんじゃないかって。もしあのときあなたと結婚していなかったら、もし別の相手と暮らしていたら、どんな人生があったかなって。」
彼女は高校のときに出会った初恋の相手と大学を出てすぐに結婚しました。
だから、働いたこともなければ、他の男とつきあったこともありません。
彼女はいまの生活に満足していますが、それでも別の人生もありえたかもしれないと思うと、いてもたってもいられなくなります。
勿論、彼女は具体的に離婚したいとか別居したいとか思っているわけではありません。
だが、自らの思いに何らかの形でけりをつけないかぎり、このまま夫との生活を続けることはできないと思っています。
彼女の不安は中年の精神的危機と言えるかもしれません。
しかし、そのような思いは、年齢に関係なく、人生の節目節目で誰にでも訪れるものではないでしょうか。
だから、彼女の危機はみかけほど軽いものではありません。
夫は妻の気持ちを十分に理解しているとはいえませんが、それでも妻の心が自分から離れかけていることを感じています。
だから、妻を取り戻そうと必死になるのです。
② 夫はどのようにして妻を寝室から出てこさせるか
夫は鈍感で天然ぼけの男ですが、結婚して19年たったいまも妻を心から愛しています。
妻はおそらく「これでよかったんだ。」「お前の選択は間違っていなかった。」と言って欲しいのでしょう。
しかし、誠実であろうとすればするほど、そのようなことは言えません。
彼にできるのは、妻の話を聞いて理解しようとすることだけです。
「俺はだめな男だ。こんなに近くにいながら、君の気持ちがわからなかった。」、「ただ、理解はできなくても、理解しようとすることはできる。こうして君の話を聞くことはできる……それじゃだめかな。」と男は言います。
恋人であれ、夫婦であれ、友人であれ、人と人とはわかりあえないものなのかもしれません。
しかし、わかろうとすること、人と人との間にある溝を超えようとすることこそが「愛」なのではないでしょうか。
夫のそのようなひたむきさがわかったからこそ、妻はいままで誰にも話したことのない「秘密」――中学生のときに見た映画の話――を打ち明けます。
映画の思い出は他人からみればばかばかしいものかもしれませんが、彼女にとっては何より大切なものです。
夫はその話に耳を傾けるだけでなく、それに刺激されて彼もまた、自分にとって大切な(場合によってははずかしい)「秘密」を打ち明けます。
妻の精神的危機は克服されたわけではありません。
しかし、お互いがいままで一度も話したことのない「秘密」を打ち明けたことで、彼らは再び一緒に生きることができるのです。
③ 友人、田中の役割
この芝居は夫婦の愛の物語であると同時に、男と田中の友情の物語でもあります。
田中は漫才でいう「つっこみ」であると同時に、きっかけを与える人物です。
彼がいるからこそ夫は夫婦の歴史を振り返るし、彼が最初に自分の「秘密」――洋子への思い――を打ち明けるからこそ、洋子も自分の「秘密」を打ち明けます。
ある意味で、彼はとてもかわいそうな人物です。実際また、最後に夫婦へのうらみつらみを口にもします。
しかし、別な意味では、幸せな男でもあります。
彼は言います――「俺は本気で思ってるんだ、恋の相手はいくらでもいるけれど、一生付き合える友だちはそうたくさんはいない。
お前がいて、洋子ちゃんがいて、俺がときどき遊びに来て、三人で酒飲んで、馬鹿話して……それでいいじゃないか。
だから……喧嘩しないでくれよ。仲直りしてくれよ、俺のために。」
洋子への彼の思いが報われることはありませんが、少なくとも彼のこの望みは叶ったのです。
だから、彼は納得して、夫婦のためにハンバーグを作ります。
④ 結末のもつ意味
結末では最初の場面が夫と妻の立場を入れ替えて繰り返されます。
しかし、それは3人が生きた時間――それぞれが心の奥底に秘めた「秘密」を打ち明けあった時間――がむだであったことを示すものではありません。
人生は流れていきます。すべての問題が一挙に解決されるなどということはありえません。
上に述べたように、洋子の精神的危機は一時棚上げされただけで、解決されたわけではないのです。
だが、3人が生きた特別な時間――それは一生に何回かしかない特権的な時間です――は確実に存在しました。
この芝居の結末はそのようなことを示しています。
この芝居は近所のラーメン屋で生まれました。
ラーメンを食べているとき、竹内まりあの「家に帰ろう(マイ・スウィート・ホーム)」が流れてきたのです。
私は竹内まりあはそれほど好きではなく、聞くとはなしに聞いていただけですが、「偽りだけの恋ならば/百回でもできる/それならふたり/ここで暮らそう/百歳になるまで」というフレーズを聞いて思わず涙が流れてきました。
男が新婚旅行から帰ってきたとき、妻を抱きかかえながら「ここでふたり百歳になるまで暮らそう」と言ったというエピソードはそこから作りましたし、タイトルを「マイ・スウィート・スウィート・ホーム」にしたのもそのためです。
この芝居は特定の、あるいは特別な夫婦の物語ではなく、どこにでもいる夫婦の話です。
だから、当初、登場人物に名前はつけないつもりでした。
ただ、実際に書き始めてみると、ふたり芝居ならいざ知らず、3人芝居で全く名前を呼ばないというのはかなり無理があることに気付きました。
そのため妻には洋子、友人には田中という非常に平凡な名前をつけました(全国の洋子さん、田中さん、気を悪くしたらごめんなさい)。
男に名前がないのは、そういう理由からです。
作者が作品について語るのは野暮だと最初に書きましたが、がっちり語ってしまいました。
観て下さったお客さまがどう感じられたかは、私にはわかりません。
ただ、私の意図のいくぶんなりとも伝われば、作者としてこれほど幸せなことはありません。
あ、最後にもうひとつだけ――私は芳本美代子さんのファンです。写真集を2冊もっています。
作者が作品について語るのは野暮かと思いますが、あの芝居のねらいは次の3点でした。
・ 恋は若者だけのものではない、中年や熟年の男女も若者と同じようにひとを愛するし、また愛されたいと願うものだということを示したい。
・ 「自分の人生はこれでよかったのか」、「別の人生もありえたのではないか」という不安、人生の節目に誰にでも訪れうる精神的危機を描きたい。
・ いい年をした男女が必死になってばかなことをしている或る意味みっともない姿に人間のみじめさと、その奥に潜む真実を示したい。
ポイントとしては次の4つを挙げることができます。
① 妻(洋子)は何に怒っているのか
② 夫はどのようにして妻を寝室から出てこさせるか
③ 友人、田中の役割
④ 結末のもつ意味
順を追って説明いたします。
① 妻(洋子)は何に怒っているのか
妻は決して夫に対して怒っているのではありません。彼女は言います――
「あなたと結婚したことを後悔してるわけじゃない。あなたのためにご飯をつくったり掃除をしたり洗濯をしたりするのも、決していやじゃなかった……
でもね、この歳になるとふと思うことがあるの、別の人生もあったんじゃないかって。もしあのときあなたと結婚していなかったら、もし別の相手と暮らしていたら、どんな人生があったかなって。」
彼女は高校のときに出会った初恋の相手と大学を出てすぐに結婚しました。
だから、働いたこともなければ、他の男とつきあったこともありません。
彼女はいまの生活に満足していますが、それでも別の人生もありえたかもしれないと思うと、いてもたってもいられなくなります。
勿論、彼女は具体的に離婚したいとか別居したいとか思っているわけではありません。
だが、自らの思いに何らかの形でけりをつけないかぎり、このまま夫との生活を続けることはできないと思っています。
彼女の不安は中年の精神的危機と言えるかもしれません。
しかし、そのような思いは、年齢に関係なく、人生の節目節目で誰にでも訪れるものではないでしょうか。
だから、彼女の危機はみかけほど軽いものではありません。
夫は妻の気持ちを十分に理解しているとはいえませんが、それでも妻の心が自分から離れかけていることを感じています。
だから、妻を取り戻そうと必死になるのです。
② 夫はどのようにして妻を寝室から出てこさせるか
夫は鈍感で天然ぼけの男ですが、結婚して19年たったいまも妻を心から愛しています。
妻はおそらく「これでよかったんだ。」「お前の選択は間違っていなかった。」と言って欲しいのでしょう。
しかし、誠実であろうとすればするほど、そのようなことは言えません。
彼にできるのは、妻の話を聞いて理解しようとすることだけです。
「俺はだめな男だ。こんなに近くにいながら、君の気持ちがわからなかった。」、「ただ、理解はできなくても、理解しようとすることはできる。こうして君の話を聞くことはできる……それじゃだめかな。」と男は言います。
恋人であれ、夫婦であれ、友人であれ、人と人とはわかりあえないものなのかもしれません。
しかし、わかろうとすること、人と人との間にある溝を超えようとすることこそが「愛」なのではないでしょうか。
夫のそのようなひたむきさがわかったからこそ、妻はいままで誰にも話したことのない「秘密」――中学生のときに見た映画の話――を打ち明けます。
映画の思い出は他人からみればばかばかしいものかもしれませんが、彼女にとっては何より大切なものです。
夫はその話に耳を傾けるだけでなく、それに刺激されて彼もまた、自分にとって大切な(場合によってははずかしい)「秘密」を打ち明けます。
妻の精神的危機は克服されたわけではありません。
しかし、お互いがいままで一度も話したことのない「秘密」を打ち明けたことで、彼らは再び一緒に生きることができるのです。
③ 友人、田中の役割
この芝居は夫婦の愛の物語であると同時に、男と田中の友情の物語でもあります。
田中は漫才でいう「つっこみ」であると同時に、きっかけを与える人物です。
彼がいるからこそ夫は夫婦の歴史を振り返るし、彼が最初に自分の「秘密」――洋子への思い――を打ち明けるからこそ、洋子も自分の「秘密」を打ち明けます。
ある意味で、彼はとてもかわいそうな人物です。実際また、最後に夫婦へのうらみつらみを口にもします。
しかし、別な意味では、幸せな男でもあります。
彼は言います――「俺は本気で思ってるんだ、恋の相手はいくらでもいるけれど、一生付き合える友だちはそうたくさんはいない。
お前がいて、洋子ちゃんがいて、俺がときどき遊びに来て、三人で酒飲んで、馬鹿話して……それでいいじゃないか。
だから……喧嘩しないでくれよ。仲直りしてくれよ、俺のために。」
洋子への彼の思いが報われることはありませんが、少なくとも彼のこの望みは叶ったのです。
だから、彼は納得して、夫婦のためにハンバーグを作ります。
④ 結末のもつ意味
結末では最初の場面が夫と妻の立場を入れ替えて繰り返されます。
しかし、それは3人が生きた時間――それぞれが心の奥底に秘めた「秘密」を打ち明けあった時間――がむだであったことを示すものではありません。
人生は流れていきます。すべての問題が一挙に解決されるなどということはありえません。
上に述べたように、洋子の精神的危機は一時棚上げされただけで、解決されたわけではないのです。
だが、3人が生きた特別な時間――それは一生に何回かしかない特権的な時間です――は確実に存在しました。
この芝居の結末はそのようなことを示しています。
この芝居は近所のラーメン屋で生まれました。
ラーメンを食べているとき、竹内まりあの「家に帰ろう(マイ・スウィート・ホーム)」が流れてきたのです。
私は竹内まりあはそれほど好きではなく、聞くとはなしに聞いていただけですが、「偽りだけの恋ならば/百回でもできる/それならふたり/ここで暮らそう/百歳になるまで」というフレーズを聞いて思わず涙が流れてきました。
男が新婚旅行から帰ってきたとき、妻を抱きかかえながら「ここでふたり百歳になるまで暮らそう」と言ったというエピソードはそこから作りましたし、タイトルを「マイ・スウィート・スウィート・ホーム」にしたのもそのためです。
この芝居は特定の、あるいは特別な夫婦の物語ではなく、どこにでもいる夫婦の話です。
だから、当初、登場人物に名前はつけないつもりでした。
ただ、実際に書き始めてみると、ふたり芝居ならいざ知らず、3人芝居で全く名前を呼ばないというのはかなり無理があることに気付きました。
そのため妻には洋子、友人には田中という非常に平凡な名前をつけました(全国の洋子さん、田中さん、気を悪くしたらごめんなさい)。
男に名前がないのは、そういう理由からです。
作者が作品について語るのは野暮だと最初に書きましたが、がっちり語ってしまいました。
観て下さったお客さまがどう感じられたかは、私にはわかりません。
ただ、私の意図のいくぶんなりとも伝われば、作者としてこれほど幸せなことはありません。
あ、最後にもうひとつだけ――私は芳本美代子さんのファンです。写真集を2冊もっています。
2014年12月
チーム銀河
東浦弘樹(とううら・ひろき)
チーム銀河
東浦弘樹(とううら・ひろき)
【演出後記】
東浦さんから企画・脚本をいただいたのは去年の春頃でした。
「東浦さんらしい本だなぁ」
というのが最初の感想でした。
素直で、真っ直ぐで、真剣でありながら滑稽。
「直球ど真ん中」
これが2つ目の感想でした。
展開はオーソドックス、もっと言えばベタ。
この脚本を読んだある人がこう言いました。
「現実世界の普通の人間が出てくるけど、ピュア過ぎてこれはほとんどファンタジーだ。」
正直、僕もそう思います。あまりにピュアです。
けれど、『架空の世界』という意味のファンタジーとは思っていないのです。
僕はまだ彼らのような関係性に出会ったことはありません。
僕にとって『現実ではない』。
だから『ファンタジー』なのです。
この世界のどこかに、あんな関係を築いている人たちは必ずいる。
僕たちも、観に来てくださった方々も、誰でも彼らのような関係を築くことはできる。
いつか『ファンタジー』じゃなくなる。
僕はそう信じています。
だからこそ、この脚本を100パーセントピュアな形で皆さんにお届けしたいと思いました。
「自分はどうなってもいいから、これだけは相手に伝えたい」という思い。
そんな思いをぶつけられる・受け止められる人間関係の強さ。
そんな関係が世界に増えていえばいいなぁ、という思いを込めて。
慶雲
「東浦さんらしい本だなぁ」
というのが最初の感想でした。
素直で、真っ直ぐで、真剣でありながら滑稽。
「直球ど真ん中」
これが2つ目の感想でした。
展開はオーソドックス、もっと言えばベタ。
この脚本を読んだある人がこう言いました。
「現実世界の普通の人間が出てくるけど、ピュア過ぎてこれはほとんどファンタジーだ。」
正直、僕もそう思います。あまりにピュアです。
けれど、『架空の世界』という意味のファンタジーとは思っていないのです。
僕はまだ彼らのような関係性に出会ったことはありません。
僕にとって『現実ではない』。
だから『ファンタジー』なのです。
この世界のどこかに、あんな関係を築いている人たちは必ずいる。
僕たちも、観に来てくださった方々も、誰でも彼らのような関係を築くことはできる。
いつか『ファンタジー』じゃなくなる。
僕はそう信じています。
だからこそ、この脚本を100パーセントピュアな形で皆さんにお届けしたいと思いました。
「自分はどうなってもいいから、これだけは相手に伝えたい」という思い。
そんな思いをぶつけられる・受け止められる人間関係の強さ。
そんな関係が世界に増えていえばいいなぁ、という思いを込めて。
慶雲